学パロ藤芽(小説)
- highbridge7755
- 2021年6月3日
- 読了時間: 16分
更新日:2021年6月5日
管理人のTwitterで好男子たちと芽衣ちゃんがlineしてるギャグを繰り広げたのがきっかけで、あの藤田さんがlineグループに入ってくる経緯を妄想過多で垂れ流してます。
詳しくはpixivのギャグ詰めを見るといろいろあります。
本編のあと番外編もあり。
⁂
『私も懲りないなぁ…』 終業式が終わってしばらくした後、保健室へと足を運びながら、私は自分に呆れていた。 本当は、クラスメイトに終業式後吉野さん家に行こうと誘われ、決意が激しく揺らぎそうになってしまったが、それを振り切って向かう事ができた。 …迷惑がられると知っていても、 ただ、あの人に会いたくて。 高校2年生最後の日、もう何度目になるか分からない道を辿りながら、見慣れたドアの前に立つ。 日が暮れ始めている部屋は、薄明かりが点いていて、 藤田先生がまだいるのを確認してから、私はゆっくりと引き戸を開けた。 入学式の日、初めて見かけた時は、ただひたすら「怖い」と思った。 何せたった今から入学しようという新入生の身だしなみの取り締まりを校門でしていたのだ。 左手に木刀を持ちながら仁王立ちで。なんとも容赦がない。 入学初日からスカートを短く履いたりボタンを開けて来る強者は居なかったみたいなので(ごく一部横山くんをのぞいて)、 その左手に持つ木刀が奮われる事はほぼなかったようだが、新入生は口々に「目が合っただけでしょっぴかれそう」と恐怖におののいていた。私もその一人だった。 そのイメージが覆ったのは、夏の気配漂う初夏の、高校入学して初めての調理実習の授業中だ。 私が誤ってまだ熱い鍋のフチに触れてしまって、指を火傷してしまったのだ。 藤田先生がすっ飛んできて冷蔵庫から持ち出した氷を指にあてて、 「しばし自習にする。」と一言告げて私の手を引いて保健室へ連れて行った時は、まさに騒然だった。 それからの対応も迅速かつとても丁寧で綺麗な処置だったので、「ただ怖いだけの人じゃないのかもしれない」と思った。 そして処置が終わり、「ありがとうございます」と私がペコリと頭を下げた時、思いがけない事を言われた。 「お前、よく授業中に金縛りに遭っているだろう」 「―――なぜそれを!?!?」 「いつも必死に俺の板書を追って書いていると思ったら、脂汗を垂らしながら微動だにしない時があるからな。俺も夜寝ている時に金縛りに遭う時がある。」 「……それって…藤田先生ももしかして幽霊が…?」 「いや、俺は見えない。気配を感じるぐらいはできるが、お前は視えるのか」 「う…あ、…はい……」 高校こそは誰にもバレずに過ごそうと思っていたのに、今の聞き方は完全に自分が視える事を教えている言い方だった。我ながら間抜けすぎて呆れてしまう。 まさかこんなに早く誰かに視える事がバレるとは思っていなかった。 また変な噂が広まってしまったらと思うと、胸がズキズキと痛む。 これからの高校生活が不安で仕方なくなってきた私に、藤田先生はさらに思いがけない言葉をかけた。 「理事長の話によると、この学校は他の高校よりも多く『いる』らしい。家庭科の授業以外の時は大抵保健室にいるから、体調が悪くなったらいつでも来い」 「え……?」 「別にお前の事を誰かに言いふらしたりもせん。俺にはどうでもいい事だからな」 それからはよく保健室へ通うようになった。 特に5限目などの夕暮れ時の授業にさしかかると、霊の姿も見えてくるので授業に集中できない事が多く、頭痛もよくなっていたので、最後の授業が終わってすぐHRを受けずに駆け込む事が多かった。 藤田先生は剣道部の顧問も兼任しているので、私を寝かせた後退出する事がほとんどだが、一時間後ぐらいに様子を見にきてくれて、「そろそろ起きろ。暗くなる前に帰れ」と起こしてくれるのだ。 怖い人だと思っていたけれど、それは真面目な性格とあの眉間のシワと、下がるばかりで全く上がる事がない口角が原因なだけで、本当は生徒思いな人なんだなぁと、一年生の一学期が終わる頃には、藤田先生を全く怖がらなくなっていた。 それどころか、夏休みが明けて二学期からは、授業のスピードが早すぎてイマイチ理解がしきれていなかった家庭科の授業を、より気合いを入れて受けるようになって、授業のあと藤田先生に質問する事も増えた。 その甲斐あってか、平均点がいつも40点を下回るというあの難関すぎる家庭科のテストを、一年の学期末テストでは70点越えができた。 その時のテストを返却された時の藤田先生の顔は、一生忘れられない。 ほんの少しだけだけど、 目は細められ、口角が上がっていたのだ。 2年生になって、鏡花さん達と同じクラスになった時、夕暮れになってすぐに鏡花さんの肩に乗ったウサギを見つけて飛び上がってしまい、ついに高校2年目にして私が視える人だとバレてしまった。 でも、新しいクラスの人たちは、そんな私を受け入れてくれた。 鏡花さんが「見えるからなに?他の人より出会いの数が多いだけだよ。」と豪語してくれたおかげかもしれない。 他の人には視えないモノが視えてしまう私を、特に咎めたりバカにしたりもせず、忌み嫌ったりもしないで、皆が受け入れてくれた。鏡花さんという視える仲間もできた。 本当に嬉しくて、その日は全く体調が悪くないのに授業が終わるやいなや 「すみません!保健室行きます!!」と新しい担任の森先生に告げ、駆け足で保健室へ行った。 勢いよく扉を開けた私に、 「…今日は全く体調が悪くなさそうだが」 と藤田先生が呆れたように言っていたのをよく憶えている。 「ごめんなさい!どうしても藤田先生にお話ししたくて!!あのっ私、新しいクラスで――――」 事の成り行きを興奮気味で、支離滅裂になりながらも堰を切ったように話した私を、藤田先生は、 「…良かったな」 とだけ告げた。 私が今まで一度だって見たことがない、 優しい微笑みを添えて。 それからは完全に藤田先生の事を意識し始めてしまった。 授業中目が合うような事があれば自分でもびっくりするぐらい顔を熱くして思いきり逸らしてしまうし、そのくせ校内で姿を見かけると、姿が見えなくなるまで目で追ってしまったり。 家庭科の授業がなくて藤田先生を見かけられない日なんて、あの春草さんに 「君、まるで牛丼を一週間食べれてないみたいにゲッソリしてるけど、大丈夫?放課後吉野さん家行く?」 と声をかけられてしまうぐらいだ。 だから、テスト前になると、私は家庭科の授業がない日でも休み時間に職員室へ行って、藤田先生に今回のテストについて色々質問しに行ったりするようになっていた。 良い点数を取りたいのもあるけど、ただ、会ってお話がしたくて。 会うたび、目が合うたび、言葉を交わすたびに、鼓動がトクンと跳ねる。 その感触が心地よくて。 「お前はよく俺に質問しに来るが、他の教科は大丈夫なのか。」 ある秋の期末テスト前、藤田先生がふと聞いてきてしまった。 「………」 実はあんまり大丈夫ではなかった。数学や日本史も割りといつも赤点スレスレの成績なので、 「えーと、、ちょっと数学と日本史も、苦手かもしれないですけど…、大丈夫です!なんとかします!」 と精一杯の笑顔で答えると、 「数学と日本史か…それなら俺でも教えられそうだな」 …ん?? 思わず目をみはった。 「えぇと…?」 意味がよく理解できず聞き返すと、 「放課後保健室に来い。」 それだけ言って藤田先生は机に向き直ってしまった。 放課後、保健室へ行くと、藤田先生は捻挫のような怪我をした男子生徒に処置をしている最中だった。 丁寧に包帯を巻き、「もういいぞ」と言われた生徒は 「ありがとうございました!」とペコリと頭を下げて保健室を出ていく。 「来たか」 「…!あ、はい!」 よく分からずに返事をして、先生の側に駆け寄ってみて気づく。 ………机の上に、家庭科と、 数学と日本史の教科書が置いてある……。 …んん???? 身体を横に傾けんばかりに首を大きく傾げていると、 「ここに座れ」 すぐ隣に置かれた丸椅子を指差された。 …これは…もしや…? 「あの、藤田先生…これは一体…?」 恐る恐る確認する。 「ついでだ。 家庭科だけ成績が良くても良い大学には行けんからな。 数学と日本史も教えてやる。」 そこからはなんとテスト前は藤田先生の個人指導が入ってしまった。 テスト前は部活がなくなるから怪我をする生徒は激減するとは言え、何かしらのトラブルで訪ねてくる生徒もいるので こんな光景を見られたらどうなってしまうだろうかと、そして何よりもこの丸椅子のすぐ隣に藤田先生がいる事に私の心臓が保たない。 おっかなびっくりハラハラしながらなんとか教えてもらった事をノートに取り頭に叩き込んでいた。 一度、教えてもらっている時に奇しくもクラスメートが保健室を訪ねてきた事がある。 しかし藤田先生はさも何か変な事があるだろうかと言わんばかりに、ごく自然に椅子から立ち上がり「どうした。」と対応をしていた。 入ってきたクラスメートは私を見て少し驚いた顔をしていたが、 何か相談事かと思ったらしく、特に言及をせずそのまま藤田先生と向き直って症状を話していた。 ――――そして月日は現在に至る。 今日は個人指導がある訳でも、私がどこか体調が悪いわけでもない。 しかし、私は今までで一番緊張した面持ちで 暮れ泥みつつある保健室を訪ねていた。 「…最近は何もないのに来る事が増えたな」 藤田先生は、私が来ることが分かっていたかのように静かにこちらを見ていた。 「そんな事ないですよ。 この前は学期末テストの自己採点を手伝って頂きましたし、 今日は、2年間のお礼を言いに来ました」 「礼などいらん」 「私がしたくて勝手にやっているだけです」 そして 「2年間、ご指導ご鞭撻を本当にありがとうございました。 藤田先生のおかげで、無事に3年生に進級できましたし、成績が凄く伸びました。 本当に感謝しています。」 と頭を下げながら、 昨日自分で作ったクッキーを差し出した。 「…これは…?」 「知ってましたか? 実は私、料理部員なんですよ。 あんまり出席できてないですけど…」 「…そうか。」 とりあえずもらっておく。とでも言われるのかなと思っていたら 「今食べてもいいか」 と聞かれ、息を呑んだ。 「………はい」 ゆっくりと顔を上げてそう答えると、 藤田先生は包みを丁寧に開き、星形のクッキーを手に取り、口に運んだ。 「……………甘いな」 「お口に合わなかったですか……?」 「そうは言っていない」 「「…………」」 その場で食べてもらえた事が嬉しすぎて私は赤くなっているであろう顔を隠すように俯き、藤田先生は気恥ずかしいのか顔を横に背けていた。 少しばかり顔が赤く見えるのは、夕日のせいだろうか。 それでも、クッキーは黙々と食べていてくれていた。 たまらず私は本題に入った。 「あの、3年生になると 家庭科の授業が凄く減ってしまいますけど、これからも変わらずここで勉強を教えて頂けたら、すごく嬉しいです」 「…3年となると、数Ⅲは俺は学んでいないから教えられんぞ。それに日本史だって、受験を本番に迎える事になるのだから、きちんとその担当教師に聞きに行った方が良いだろう」 藤田先生は食べる手を止め、こちらに向き直った。 「私は理数系じゃないので数Ⅲは取る予定はないので大丈夫です。 それに藤田先生、スピードは早いですけど、教え方が凄く上手なんですよ。 私は藤田先生に教えてもらった方が分かりやすくて助かります。 日本史だけでも、お願いしたいです」 「……そうか 考えておく。」 それだけ言うと藤田先生は窓に手をかけ、 「もう暗くなる。お前は帰れ。」 と私を促した。 「……あの! もうひとつだけ…いいですか…」 「なんだ」 閉めかけた窓にふと手を止め、 藤田先生は私に背を向けたまま応じた。 私は拳をぎゅっと握りしめて、震えそうになる声を抑えて言った。 「………もう気づいてると思いますが… 私は、……藤田先生の事が、 好きです。 先生としても一人の人間としても、 尊敬しています。」 「―――!?」 目を丸くして振り向いた藤田先生を見上げながら、私は震える拳を胸の前で握り締めて続ける。 「安心して下さい。先生とどうこうなろうとか思ってないです。 ただ………3年生になったらあんまり会えなくなっちゃうのかなって思って 気持ちを、伝えておきたかっただけです。 本当は卒業式の日に言おうと思ってましたが、 あと一年も… 言えずにいれそうになくて… 待ちきれなくて… ごめんなさい…」 「…綾月。」 初めてテスト返却のとき以外で名前を呼ばれたなぁ、なんて脳裏では呑気な事を思いながら、 私は堰を切ったかのように溢れ出る想いを抑えられずに続けた。 「これでもう先生は私に教える気がなくなってしまったかもしれませんが、 それでも伝えておきたかったんです。 どの道私は生徒で先生は教師だから、何も変わりません、変わりたいとも思ってません。 独りよがりに気持ちを伝えたかっただけです。 困らせると分かっているのに勝手でごめんなさい。 …ただ、 ずっと、 ずっと、 好きでした。 先生の事が―――」 そこで言葉が紡げなくなった。 先生が、私の唇を塞いだからだ。 先生の唇で。 「――――――っ………」 思考が止まる。 頭が真っ白になる。 カーテンが揺れる。 先生の長い髪が、ゆっくりなびく。 微かにクッキーのバターの匂いと 砂糖の甘い味がした。 ―――ほんの数秒の事かもしれない。 でも、二人の時間は確実に止まっていた。 永遠にも思える時間の中、 藤田先生はゆっくりと私の唇から自分のそれを離し、 まだ鼻と鼻がぶつかりそうな至近距離で、 今まで見たことがないような熱い視線を私に向けた。 「………本当に、 困った娘だ」 そう言って こんな筈じゃなかった、と言わんばかりの 苦虫を噛み潰したような表情で顔を横に背ける。 今度はハッキリと顔が赤いのが分かった。 「先、生……」 私はそれしか言えなかった。 唇が震えていた。 その唇を藤田先生はゆっくりと親指でなぞりながら、 「いいか。 もう二度とそのような事を口にするな。 お前は生徒で俺は教師だが… その前に俺は一人の男だ。 俺はお前が思っている程できた男ではない。 …それを忘れるな。」 この行為や発言の意味が分からない程、私は鈍くはなかった。 私は、卒業式の日までこれ以上の気持ちを堪える事を心に決め、 「…はい………」 とだけ返事をした。 その日から、藤田先生とぽつぽつと個人LINEをするようになり、 藤田先生が『3年B組』というグループLINEに入ってきたのは、翌月の新学期、始業式の日からだ。
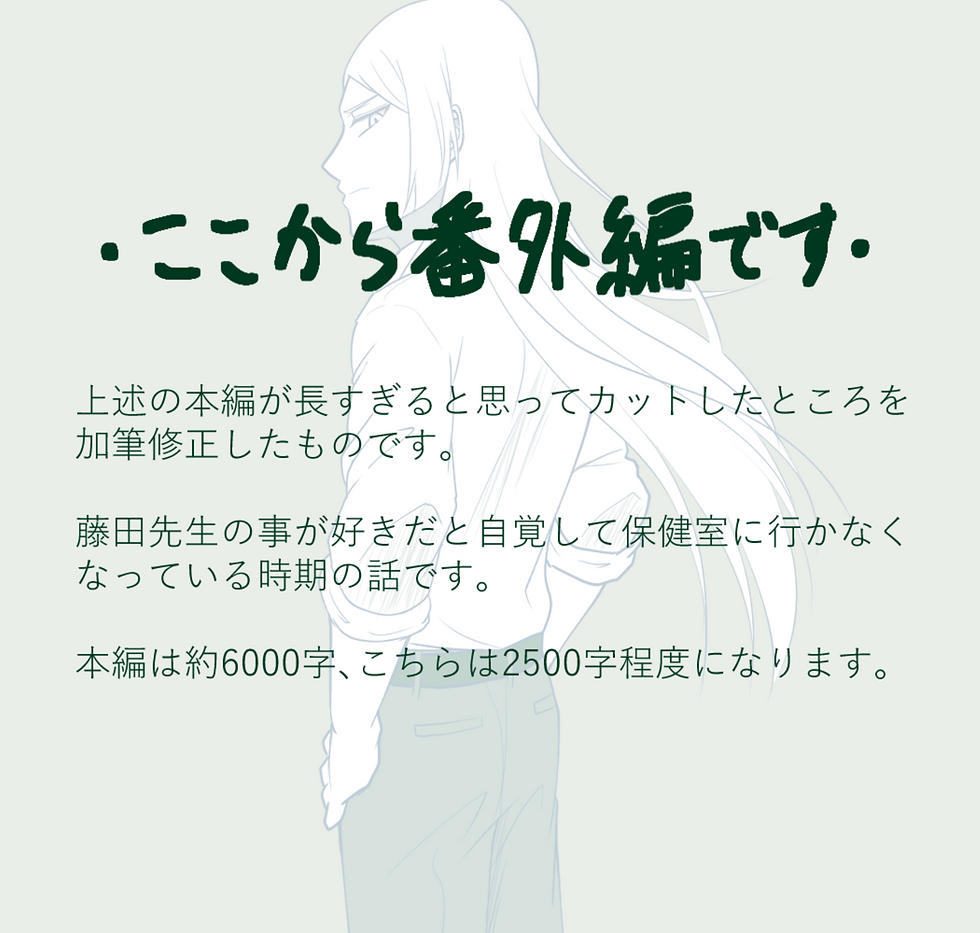
2年生になって数ヶ月が過ぎたある梅雨時の家庭科の授業中の事。
いつものように黒板に物凄いスピードでサラサラとチョークを走らせていた藤田先生が、
ふと白衣を翻し教室内を振り返った。
そのまま教室の真ん中を突っ切るように歩いたかと思えば、
一番後ろの右端、つまり私の席の目の前まで来て、
「ーおい。」
私の手首を掴んだ。
あまりに突然の事で心臓が破裂するかと思った。
クラスメイト全員がこらちを見る。一体何事かと。
「お前、今体調が良くないだろう。なぜ申告しない」
「……」
仰る通り私は激しい頭痛と寒気に襲われていた。
今はお昼休み直後で一番暖かい時間のはずなのに、
私の周りの空気だけ異様に寒いし、何やら声が聴こえるのだ。
でも、藤田先生の授業は難しいから
どうしても板書を全て完壁に書き留めておきたかったのと、
先月あった抜き打ちの小テストの点数が芳しくなかったので、
尚のこと頑張りたいと思っていたのだ。
答えられない私に対し、藤田先生は短いため息を吐いた後、
いつか聞いた時と同じ抑揚で、「しばし自習にする。」とクラスに告げた。
「どうして私の体調が悪いって分かったんですか?」
保健室に着いて、聞いてみた。
「顔が真っ青だった。いつものお前を見ていればすぐ分かる事だろう」
……いつもの私?
…それは、私の事を見ていてくれてるからそんな事が言えるのでは、と、調子の良い勘違いをしてしまいそうになる。
「最近保健室に来ていないのは、霊的な被害が減ったからだと思っていたが、違うようだな。」
私を向かいに座らせた藤田先生が、白湯を私に差し出しながら言った。
私はそれを受け取り、「ありがとうございます…」とだけ言うと、
「昨日の体育の時間でもお腹を抑えて辛そうにしてただろう。
ここから見えていたぞ。」
「あ、あれはお昼ご飯を食べ過ぎてしまって…」
「は?」
私の間抜けな発言に藤田先生は呆気に取られたような顔をしていた。
貴重な表情が見られて私は不謹慎にも内心少し喜んでしまった。
はぁぁぁ、と藤田先生は呆れたように長いため息をし、
「とにかく、体調が優れないのなら授業中だろうが担当の教師に申告しろ。
そもそも、お前は何故最近保健室に来ない。何か事情があるのか」
「……」
――貴方といると、ドキドキするんです。
…なんて言えるはずもなく。
私は答えられずに目を泳がせた。
藤田先生は黙って私を見ていた。
「……とりあえず横になれ。頭痛が辛いのだろう」
「…はい、ありがとうございます」
それ以上言及されなくて内心ホッとしながら、私はお言葉に甘えさせもらって横になった。
ーキーンコーンカーンコーン…
授業が終わった事を告げるチャイムが鳴る。
授業の後半を自習にさせてしまった事が申し訳なくて、
「授業の邪魔してごめんなさい…」
と横を向いてその背中に謝った。
藤田先生はなにやらPCを立ち上げながら、
「気にするな。
家庭科などなくなっても大した影響はない。
とにかくお前は寝ていろ。」
そう言ってキーボードをカタカタと打ち込み始めた。
何かプリントを作っているのだろうか。
私はベッドのカーテンの隙間から見えるその背中をこっそりと眺めていた。
……あぁ、私は本当にこの人の事が好きなんだなぁ。
と、しみじみ思った。
なぜ今思ったのか全く分からないけれど、
かけられた布団の暖かさと、シトシトと降る雨の音、
長い深緑色の髪が
キーボードの音に合わせて微かにサラサラと揺れるこの穏やかな時間も含めて、
今見つめている背中に抱きつきたくて仕方がなくなってしまった。
私はこの想いを、卒業まで抑えていられるのだろうか。
それが怖くて最近は保健室に行かなくなっていたのだけれど。
やっぱりこうやって会ってしまうと、
嬉しくて、嬉しくて。
今すぐにでも「好きです!」と叫んでしまいたい。
『…大好きです。』
その想いを心の中で叫びながら、
私はただひたすら、
愛しい背中を見つめていた。
「ーーーおい、起きろ」
「あれ…?」
いつの間にか眠ってしまっていたらしい。
もうすっかり夕暮れ時になっていた。
「体調は良くなったか。」
「…あ、はい!」
自分が頭痛だった事をすっかり忘れていた。
背中を見つめていたらそれだけで幸せすぎてとっくに治っていたんだと思う。
「ならば日が暮れる前に帰れ」
「あの、藤田先生はこの後は…?」
「俺は職員室に戻る。まだやることがあるからな」
よく見ればいつの間にかPCは畳まれ、机の上も綺麗に整えられている。
そのまま立ち去ろうとする藤田先生の白衣の裾を、思わずつまんだ。
「ーどうした」
「…あ、えっと…その…
私なにか寝言とか言ってませんでした?」
「特に言っていなかったと思うが」
「わ、分かりました。引き留めてごめんなさい」
「…また明日」
「…はい!また明日」
『また明日』なんて言われた事がなくて、つい嬉しくて満面の笑みを返してしまった。スキップしそうな勢いでその場を去る。
『…あれは、夢だったのかな。』
いつの間にか完全にスキップになっていた足が止まる。
おそらく藤田先生に起こされる少し前、
夢うつつの中で…
頭を撫でられていた気がする。
髪を鋤かれ、
頬に触れられ、
耳元で
『ーーお前のその視線は、
どうにかならんのか。
授業中も感じるぞ』
確かにそう聞こえた。
そして、さらに低い声で
『…どうにかしてやりたくなる』
思い出した途端耳まで真っ赤になった顔を覆い、
私は暮れ泥む渡り廊下を全速力で走った。


Comments